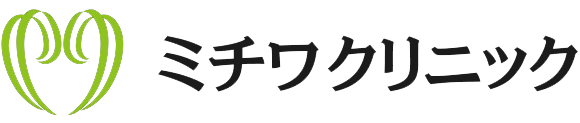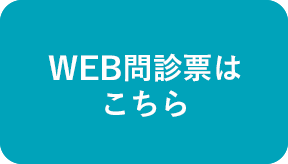不安障害と自律神経失調症の関係について
〜心と体がつながっているということ〜
現代社会では、「不安」や「ストレス」を感じる人が多く、それが原因で体や心にさまざまな不調が出ることがあります。中でも「不安障害」と「自律神経失調症」は、よく聞く言葉かもしれません。実はこの2つの症状は、密接に関係しています。ここでは、両者の特徴や関係性、そしてどのように対処すればよいかについて、専門的な知見をやさしく解説していきます。
*不安障害とは?
不安障害とは、「過剰な不安や心配」が日常生活に支障をきたす状態のことをいいます。例えば、
・些細なことが気になって仕方ない
・理由がないのに突然強い不安に襲われる(パニック)
・他人の目が過剰に気になる(社会不安)
といった症状が長く続く場合、不安障害と診断されることがあります。
通常の「不安」は誰でも感じる自然な感情ですが、不安障害ではその強さや持続時間が極端で、日常生活・仕事・人間関係に大きな支障を及ぼすようになります。
*自律神経失調症とは?
自律神経失調症とは、自律神経のバランスが乱れて、体にさまざまな不調が現れる状態です。自律神経とは、自分の意志とは関係なく体の働きを調整してくれている神経で、以下の2つがあります。
・交感神経:活動・緊張モード(昼間やストレス時に働く)
・副交感神経:休息・回復モード(夜やリラックス時に働く)
このバランスが崩れると、以下のような症状が出ることがあります。
・めまい・頭痛・吐き気
・胸がドキドキする、息苦しい
・手足の冷え、のぼせ、発汗異常
・お腹の調子が悪い(下痢や便秘)
・眠れない、疲れやすい
病院で検査をしても原因がはっきりしないのに、これらの症状が続くとき、「自律神経失調症」と診断されることがあります。
*不安障害と自律神経失調症はどう関係しているの?
共通点がたくさんある
不安障害と自律神経失調症は、一見すると別の病気のように思われがちですが、実はとても深い関係があります。どちらも、ストレスや心理的な負担が大きく関係しており、自律神経のバランスが崩れることで体に不調が現れるという共通点があります。
たとえば、強い不安を感じたとき、人の体は「闘うか逃げるか(fight or flight)」という防御反応をとります。これは交感神経が急激に働いて、心拍数が上がったり、呼吸が浅く早くなったりする反応です。
この状態が長く続くと、自律神経のバランスが崩れてしまい、体のさまざまな場所に不調が出てきます。つまり、「不安」から始まった心の反応が、体の病気のような症状として現れてくるのです。
症状の出方に違いがあるだけ
不安障害では「心の症状」が中心になりますが、それにともなって体にも症状が出ます。一方、自律神経失調症では「体の症状」が目立ちますが、その背景には強い不安やストレスがあることが多いです。
つまり、どちらが「原因」でどちらが「結果」というわけではなく、人によって症状の出方が違うだけなのです。心と体は切り離せないということです。
*不安があると自律神経も乱れる
私たちが不安を感じると、脳の中にある「扁桃体(へんとうたい)」という部分が反応して、「危険が迫っている」と体に指令を出します。すると交感神経が活発になり、心拍数や血圧が上がったり、汗が出たりします。
これは本来、短時間だけ働くはずの反応ですが、慢性的な不安があると、いつも体が緊張モードになってしまいます。その結果、自律神経が疲れてしまい、バランスが崩れてしまうのです。
◆診断と治療について
診断の難しさ
不安障害も自律神経失調症も、「病気らしい異常」が検査で見つかりにくいという特徴があります。そのため、
- 心療内科や精神科
- 内科、耳鼻科、循環器科
など、いろいろな診療科を回っても、なかなか原因がはっきりしないということがよくあります。だからこそ、体の症状だけでなく「心の状態」もきちんと医師に伝えることがとても大切です。
治療について
不安障害も自律神経失調症も、「心と体の両面から治していく」ことが重要です。
- 薬による治療
不安が強い場合は、抗不安薬や抗うつ薬(SSRIなど)を使うことがあります。また、自律神経のバランスを整える目的で、漢方薬が処方されることもあります(例:加味逍遙散、抑肝散など)。
- カウンセリングや認知行動療法
不安の背景には「考え方のクセ」や「心の習慣」が関係していることがあります。これを見直すのに役立つのが、認知行動療法(CBT)や心理カウンセリングです。思考を整理したり、現実的な見方を身につけたりすることで、不安や緊張が和らぎます。
- 心と体を整える生活習慣
生活のリズムを整えることも非常に大切です。特に、
- 睡眠(寝る時間と起きる時間を一定にする)
- 食事(朝ごはんを抜かない)
- 運動(軽いウォーキングやストレッチ)
- ストレス発散(趣味や休息)
といった基本的なことが、自律神経の安定にはとても効果的です。
まとめ
不安障害と自律神経失調症は、心と体のバランスが乱れたときに起こる病気です。名前や症状の出方は違っていても、その根本には「不安」「ストレス」「自律神経の乱れ」といった共通の問題があります。
心の問題が体に出ることもあれば、体の不調が不安を悪化させることもあります。そのため、心と体を切り離さずに、総合的にケアしていくことがとても大切です。
「こんなことで病院に行っていいのかな」と悩む必要はありません。不安や体の不調を我慢せず、心療内科や専門医に早めに相談することをお勧めいたします。
院長 佐久間一穂
新着情報
- 2025.12.24
- 院長ブログ何もしたくない日が続くのは、甘えではなく「うつ病」の可能性あり
- 2025.12.18
- クリニックのお知らせ🎍年末年始休診のお知らせ🎍
- 2025.12.17
- 院長ブログ不安が止まらない…それ、不安障害かもしれません|原因・症状・治療を医師目線で解説
- 2025.09.02
- クリニックのお知らせ臨時休診のお知らせ
- 2025.06.18
- 院長ブログ双極性障害とADHDの違い・類似点、併存する場合を医学的に解説:似て非なる2つの疾患
- 2025.06.15
- 院長ブログ自分でできる双極性障害チェック ― MDQ(ムード障害質問票)とは?