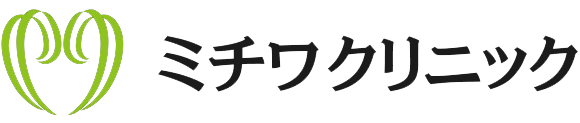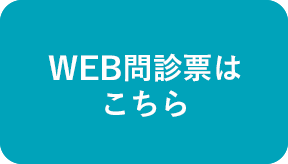双極性障害は誤診されやすい?うつ病との違いとは
双極性障害(Bipolar Disorder)は、かつて「躁うつ病」とも呼ばれていた精神疾患で、気分が高揚する「躁(そう)状態」と、気分が落ち込む「うつ状態」とを周期的に繰り返す特徴があります。日本では100人に1~2人が生涯で発症するといわれ、決して珍しい病気ではありません。
ところが、この双極性障害は「うつ病」と誤診されることが非常に多く、診断の遅れが適切な治療の開始を妨げることもあります。特に「双極II型障害」と呼ばれる軽躁とうつを繰り返すタイプは、外見上「うつ病」と酷似しているため、見分けが困難です。
本記事では、双極性障害とうつ病の違いを中心に、診断の難しさや誤診が起こる背景、診断に役立つポイント、治療方針の違いなどを解説していきます。
<1>双極性障害とうつ病 ― 定義と分類
1-1. 双極性障害とは?
双極性障害は、大きく以下の2つのタイプに分類されます。
・双極I型障害(Bipolar I Disorder)
明確な「躁状態(manic episode)」が1回以上あり、うつ状態も併発するケースが多い。
・双極II型障害(Bipolar II Disorder)
軽躁状態(hypomania)とうつ状態を繰り返すが、完全な躁状態には至らない。
1-2. うつ病(大うつ病性障害)とは?
うつ病は、持続的な抑うつ気分、意欲の低下、興味の喪失、睡眠・食欲の変化、自責感などを特徴とする疾患で、以下の条件により診断されます。
・抑うつ気分または興味の喪失が2週間以上持続
・社会的・職業的機能に著しい障害をきたす
・明確な躁や軽躁エピソードを一度も経験していないこと
<2>双極性障害が誤診されやすい理由
2-1. 多くの患者がうつ状態で初診を受ける
双極性障害の患者の約60~70%は、最初に医療機関を受診する時点では「うつ状態」であることが多く、躁的なエピソードの既往を話さなかったり、自覚していなかったりするケースもあります。そのため、うつ病として診断されてしまうことが珍しくありません。
2-2. 軽躁エピソードの見落とし
軽躁状態(hypomania)は、活動性の上昇や社交性の増加、睡眠時間の減少、思考の加速といった変化がみられますが、本人にとっては「調子がいい時期」としか感じられず、病気として認識されないことが多いです。
2-3. 質問票や診察時間の制限
診察室での限られた時間内では、過去のエピソードを正確に聴き取ることは難しく、医師が躁・軽躁の既往を見逃す要因となります。さらに、患者本人だけでなく家族や周囲の人からの情報が不足している場合、診断精度が下がります。
<3>双極性障害とうつ病の違いを見分けるポイント
3-1. エピソードの経過と特徴
|
比較項目 |
双極性障害 |
うつ病 |
|
気分変動 |
躁・軽躁とうつを周期的に繰り返す |
一貫して抑うつ状態 |
|
発症年齢 |
青年期~20代が多い |
中高年に多い傾向 |
|
家族歴 |
双極性障害の家族歴が多い |
抑うつ傾向や不安障害の家族歴が多い |
|
睡眠パターン |
軽躁期に睡眠時間が減るが活動的 |
一貫して過眠または不眠 |
|
症状の反応性 |
周囲の刺激に敏感に反応する |
感情反応が鈍く持続的 |
3-2. 疾患の経過と治療反応
双極性障害は、抗うつ薬のみで治療すると躁転(うつから躁へ移行すること)を起こしやすく、症状が悪化するリスクがあります。一方、うつ病は抗うつ薬によって比較的安定した改善が期待できます。
3-3. 自殺リスク
双極性障害は、うつ状態に加えて軽躁や躁状態後の落ち込みが激しく、自殺企図のリスクが非常に高いとされます。特に診断されずに不適切な治療を受けている場合は危険性が増します。
<4>診断のためのアプローチ
4-1. DSM-5による診断基準の確認
DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)では、双極性障害と診断するには以下のような躁/軽躁エピソードの存在が必要です。
軽躁エピソードの基準(一部抜粋)
・持続的に異常な気分の高揚、開放感または易怒性が少なくとも4日間継続
・以下の症状のうち3つ(易怒性がある場合は4つ)以上が存在
❍自尊心の誇大
❍睡眠欲求の減少
❍多弁
❍注意散漫
❍目標指向性の増加
4-2. 質問票やスクリーニングツールの活用
・ムード・ディスオーダー質問票(MDQ)
軽躁・躁エピソードの可能性を評価する簡便なツール。
4-3. 家族や同居人からの情報収集
患者本人が自覚していないエピソードについて、家族やパートナーからの情報提供は極めて重要です。特に軽躁状態の逸脱行動(浪費、性的逸脱、過活動など)に関する報告は診断の手がかりとなります。
<5>治療方針の違い
5-1. 双極性障害の治療
・気分安定薬
・抗精神病薬
・抗うつ薬の使用は慎重に
必要に応じて併用されるが、躁転リスクがあるため単剤投与は避ける
5-2. うつ病の治療
・抗うつ薬
気分の改善と再発予防を目的に使用
・精神療法(認知行動療法など)
思考パターンの修正とストレス対処力の強化
<6>誤診を防ぐために ― 医師・患者ができること
6-1. 医師側の工夫
・初診時だけでなく、継続的に過去のエピソードを再確認する
・質問票や家族面接を積極的に活用する
・抗うつ薬治療中の躁転を注意深く観察する
6-2. 患者・家族側の協力
・過去の行動や気分の変化をメモして持参する
・家族や同居人が受診に同伴することで情報精度が向上
・医師との信頼関係を築き、正確に情報を伝える努力が大切
<7>実際の診断例(症例)のご紹介
いずれも実際の臨床で見られる典型的なパターンに基づいた症例です。個人情報には配慮したうえで、疾患の理解を深める目的で編集しています。
【症例1】うつ病と診断されていたが、実は双極II型障害だった例
患者プロフィール:
年齢/性別:30歳女性
初診動機:「抑うつ気分と不眠、仕事への意欲低下が続く」
初診時の所見:
・抑うつ気分、興味の喪失、慢性的な疲労感、食欲不振、不眠が2か月ほど続いていた。
・抗うつ薬(SSRI)による治療が開始されたが、2週間後、急に元気になり多弁・多動・浪費などが出現。
その後の経過:
・薬物の副作用と考えられたが、詳細に聴取すると、過去にも似たような「気分の高まり」「夜通し活動しても平気」な期間が数回あった。
・家族面談で「急にテンションが高くなり、買い物をしすぎる」「睡眠が3時間でも平気だった」との証言。
・双極II型障害と診断され、リチウムによる気分安定化治療が開始されると、数ヶ月で安定。
コメント:
このように、抗うつ薬投与後の「躁転」がきっかけで双極性障害が明らかになるケースは非常に多く、軽躁エピソードの「質的な聴取」が重要となります。
【症例2】長年うつ病と診断されていたが、30代で双極I型障害と判明
患者プロフィール:
年齢/性別:38歳男性
既往歴:20代から抑うつエピソードを繰り返し、「うつ病」として治療されてきた
初診時の状態:
・抑うつ気分、強い罪悪感、希死念慮あり。過去にも4~5回同様のエピソードがあったと報告。
・抗うつ薬、精神療法、入院治療などが断続的に行われたが、改善は一時的。
決定的な転機:
・37歳時、突如2週間にわたりほとんど寝ずに働き、周囲にハイテンションで話しかけるなどの異常行動。
・社会的トラブル(上司との衝突、衝動的退職、浪費行動)をきっかけに精神科再診。
・面談で「昔からテンションが上がる時期が時々あった」ことが判明。
・双極I型障害と診断され、気分安定薬と向精神薬の併用により症状が安定。
コメント:
長年のうつ病としての治療歴がある場合でも、経過中に躁状態が出現すれば診断が変更されます。精神疾患では、診断は「固定」ではなく、再評価が必要です。
おわりに:正しい診断が、回復への第一歩
双極性障害とうつ病は、一見似ているようでいて、治療方針や予後に大きな違いがあります。誤診を防ぎ、適切な治療に早期にたどり着くためには、医師と患者、そして家族が一丸となって情報を共有し合う姿勢が求められます。
自分自身の気分や行動パターンに気づくこと、必要に応じてセカンドオピニオンを求めることも有効です。正しい理解と診断が、回復への最も確実な第一歩となるでしょう。
ご自身の症状に疑いがあれば、気兼ねなく早めにご相談ください。
参考文献・リソース
・American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)
・日本うつ病学会診療ガイドライン双極性障害(双極症)2023|日本うつ病学会
院長 佐久間一穂
新着情報
- 2025.12.24
- 院長ブログ何もしたくない日が続くのは、甘えではなく「うつ病」の可能性あり
- 2025.12.18
- クリニックのお知らせ🎍年末年始休診のお知らせ🎍
- 2025.12.17
- 院長ブログ不安が止まらない…それ、不安障害かもしれません|原因・症状・治療を医師目線で解説
- 2025.09.02
- クリニックのお知らせ臨時休診のお知らせ
- 2025.06.18
- 院長ブログ双極性障害とADHDの違い・類似点、併存する場合を医学的に解説:似て非なる2つの疾患
- 2025.06.15
- 院長ブログ自分でできる双極性障害チェック ― MDQ(ムード障害質問票)とは?